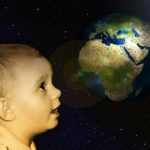「あなたが生きていくために、一番必要なものは何ですか?」
家族や友達、ペット、健康な体…。
空気とかはちょっとひねくれた答えですが、まぁ色々あると思います。
ですが、殆どの人が真っ先に思うのは、あえてここに出さなかった、「お金」ではないでしょうか。
では、
「あなたの一番大事なものは?」
必要と大事とでは、微妙にニュアンスが違います。
大事なものとなると、家族やペット、健康、時間など。
いくらお金があっても、買えないものではないでしょうか。
ですが、この社会でそれらを守るためには、やっぱりお金は必要なのが現状です。
そして、そのお金を得るために私たちは働きますが、人を助けるはずのお金が、働き方しだいでは人を苦しめる。
そんな矛盾を生み出しています。
人生の幸せは、働き方で決まるといっても過言ではないくらい、人にとっての仕事選びは大事なものなのに、本当に好きな仕事で生きている人はどれくらい居るでしょうか。
昨今、日本中で叫ばれている働き方改革ですが、仕事に対する概念は本当に大きく変わりました。
インフルエンサーは、世間に与える影響力が大きく、時代の先駆者でもあります。
これまでその役割を担っていたのは、芸能人やスポーツ選手、社会的地位の高い特別な人が主でした。
それが今では、ユーチューバーやインスタグラマーなど、赤ん坊から老人まで全くの無名であっても、アイデア1つで活躍できる、影響力者となり得るのです。
これまでの常識では考えられなかったことも、大衆の共感と賛同さえ伴えば受け入れられていく。
まさに、風の時代の特徴ですね。
今回は、有名なイソップ童話「アリとキリギリス」のお話に例えながら、本当の幸せな働き方とは何なのか。
そして3つの結末から、これからの時代にあった仕事選び、働き方を探ってみたいと思います。

目次
皮肉な教訓
昭和時代の「アリとキリギリス」のお話。
暑い夏のある日のことです。
お得意のバイオリンを弾き歌って暮らすキリギリスは、毎日重い荷物を背負いながら行進しているアリたちの姿を見て尋ねました。「君たち、この暑いなか何をせっせと運んでいるの?」
すると一匹のアリが答えました。
「僕たちは冬に備えて食料を蓄えているんだよ。」
キリギリスは驚いて、
「今は夏なんだし食料なんて周りにたくさんあるのだから、今から冬のことを気にして働く君たちは愚かだよ。」
とアリたちの行動を笑いました。
そして月日は経ち、夏が終わり寒い冬が訪れました。
草木は枯れ果て、雪に覆われた地に生命の姿はありません。キリギリスは寒さと飢えで震えていました。
雪のなかをさまよい続け、やっと見付けた一軒の家。
窓を覗くと暖かい灯りのなか、たくさんのご馳走を囲む一家の姿が見えました。「すみません。
私に食べ物を少し分けてもらえませんか。」キリギリスが家を訪ねると出てきたのは、あの暑い夏の日に自分がバカにして笑っていた、一匹の働きアリでした。
アリはキリギリスに気付くと、「食料は家族の分しかありません。
あなたは夏の間歌って過ごしたのだから冬は踊って暮らせばいい。」と扉を閉めてしまいました。
キリギリスはうなだれると、吹雪のなかへと消えていきました。
さてこのお話の教訓として考えられるのが、
- 将来に起こる危機を想定して、備えておくことで安心が得られる。
- 汗水流して働くことは尊いこと。
- お金(物質)の量は、苦労や我慢の量に比例する。
一見間違っていないようにみえますが、裏を返せば
- いつくるか分からない未来の最悪に、いつも怯えていなければならない不安感。
- 何もしないことへの背徳感。
- 楽をして、お金を得ることへの罪悪感。
きっと誰もがこういった感情を、抱いたことがあるのではないでしょうか。
戦後、日本の義務教育はまさに「アリとキリギリス」の教えでした。
社会の権力者からすれば、労働者を作るのに最も適したバイブルです。
アリのように黙って組織に貢献する人が社会の恩恵を受け、組織は大きければ大きいほど将来は安泰だと、信じられていたのです。
基準は個人ではなく、その他大勢のなかにある。
大勢と違うこと変わったことをする者は、異端者であり罪なのです。
幼少期の頃からこういったアリの思想を教えられ、それが常識になってしまうと、自分の本当にやりたいことが分からなくなってしまいます。
社会の常識からはみ出すことは、キリギリスのように扉を閉められ、吹雪の荒野へと一人立ち向かうようなものですから、委縮してしまうのは当然です。

さてイソップ童話ですが、古代メソポタミアの時代から伝承されたとも言われ、紀元前6世紀、奴隷であったアイソーポス(イソップ)が、寓話として語ったことで有名になり、広く伝えられたようです。
この「アリとキリギリス」もその一つで、元々は「アリとセミ」というお話でした。
セミのいないヨーロッパ北部に伝えられる過程で、セミがキリギリスに置き換えられ、それがそのまま日本に伝わりました。
キリギリスも夏の虫ですが秋のイメージが強く、夏はセミの大合唱が当たり前の日本では、「アリとセミ」の方がピンときますね。
しかしこのお話が、紀元前6世紀前古代から語り継がれているということに、私はとても驚きました。
イソップが奴隷という立場でありながら、こういった思想を寓話として語ったことは、権力者にとって好都合だったのではないでしょうか。
時を経て、現代にまで語り継がれた「アリとキリギリス」。
古代も現代も形は違えど、権力者と奴隷という社会の構図は変わらないのでしょうか。
このお話では、遊んでばかりいたキリギリスの悲劇はあくまでも自業自得で、アリの冷酷さに触れることはありません。
ではなぜアリは、こんなにも冷酷なことが出来たのでしょう。
アリは、提供した労働量が対価に値すると信じていたので、自分の大切な時間と体力を削りながらも、毎日の仕事を続けるしかなかったのです。
そうしなければ、これから訪れるであろう厳しい冬に、不安で夜も眠れなくなってしまうからです。
アリは、
「物資は労働しないと得られない」
という、社会の掟ともいえる作られた恐怖に、自らが奴隷となっているのです。
アリは労働に見合った対価は受け取れますが、いつも心は満たされず、自己犠牲からは執着心を生み出しました。
好きなことをして生きていたキリギリスに、自業自得という報復をすることで、自分の生き方を正当化したのでした。
昭和版「アリとキリギリス」には、このような皮肉めいた教訓が隠されているのです。
神アリ
2つめは、キリギリスを見捨てるアリの残酷さからか、改変されたお話です。
キリギリスが一家を訪ねると、出てきたのはあの暑い夏の日に自分がバカにして笑った一匹の働きアリでした。
アリはキリギリスに気付くと、「だから備えておくように言っただろ?」
と、可哀想なキリギリスを家に招き入れ、仲良くご馳走を食べました。
助けてもらったキリギリスは涙を流して改心し、お礼にバイオリンを弾きました。
現在、日本ではこちらが主流のようですが、キリギリスを赦し助けるアリは、慈愛と器の大きさを兼ね備えた、まるで神さまのようなアリです。
この改変版「アリとキリギリス」では、ただ立派なアリという理想像ではなく、なぜアリが自分をバカにした相手を許し、優しい心になれたのかを考えてみます。
一つにこのアリには、自分が働いて得た物に対して過剰な執着心がありません。
それはつまり、働くことで自分の何かを犠牲にするということが、なかったのです。
アリにとって、食べ物を運ぶという仕事は得意分野です。
アリは、自分の得意が他者に役立つことを対価にしていたので、仕事が楽しいのです。
働くことが楽しめたら、人生の殆どが楽しみで埋まってしまいます。
アリの心は満たされていたので、いくらキリギリスにバカにされても、全くもって気にはならなかったのです。
キリギリスの潔さ
「アリとキリギリス」3つ目の結末。
キリギリスが一家を訪ねると、出てきたのはあの暑い夏の日に、自分がバカにして笑った一匹の働きアリでした。
アリはキリギリスに気付くと、「あなたは夏の間歌って過ごしたのだから、冬は踊って暮らせばいい。」
と言いました。
それに対しキリギリスは、「私はもう歌うべき歌は全て歌いました。
あなたは私の亡骸を食べて生き延びればいい。」と言いました。
私は個人的にこのラストが、お話として一番好きです。
スピリチュアルでは、
「魂はこの物質世界という制限のなか、一生をかけ如何にして自分の想いを、創造するか」
という大きな目的をもって、生まれてくるといわれています。
それが例え一日の人生であろうと、百年の人生であろうと、魂は明確な意図をもって生まれてくるというのです。
このキリギリスの潔さは、そんな私たちの本質を表しているような気がします。
さて、アリはというと、キリギリスの亡骸を得て無事に冬を越しますが、また次の冬のために、来る日も来る日も身を粉にして働くのです。
冬が来る前に死んでしまうかもしれないのに、何か空しさを感じてしまいます。
では、どうすれば両者ともにハッピーになれるのでしょうか。
例えばキリギリスの心持ちを一つ変えるだけで、こんなストーリー展開が生まれます。
変えるのは、毎日バイオリンを弾いて歌って過ごしていたことではありません。
一生懸命働くアリをバカにしていた、キリギリスの心です。
キリギリスが働くアリに敬意を払い、1曲でもアリのために歌っていたら、その歌はアリにとって雑音なんかではなく、元気をくれる応援ソングにもなるのです。
応援歌は働くアリの、娯楽にも活力にもなるかもしれません。
アリたちは楽しみをくれたキリギリスに感謝して、食べ物を運んでくれます。
それが対価です。
食べ物を運んできてくれるアリのためにキリギリスは、もっともっと良い音楽を作ります。
その日から得意なバイオリンはキリギリスの仕事となり、アリは大切なお客となりました。
また働くアリにとっても活力をくれるキリギリスは、大切な存在なのです。

お互いが価値を提供することで、二つの世界が繋がり循環したのです。
- アリをバカにしてただ歌っていたキリギリス。
- アリのために得意な音楽を仕事にしたキリギリス。
どちらも夏の間歌っていましたが、結果は雲泥の差です。
成功者たちの多くが、口を揃えて言います。
対価は自分の体力や時間ではなく、自分の得意な事、好きな事、出来る事で他者の身体的、精神的欲求を満たすことで生まれる。
仕事をしている人に、これからする人に問います。
- あなたはその仕事が好きですか?
- それはあなたのしたいことですか?
- そして出来ることですか?
当てはまるなら、それはあなたの得意になる可能性大です。
ぜひ、自分の得意を活かしてみてください。
あなたの笑顔で救われる人が、必ずいますから。
🌸こちらの記事は、2019.8.30投稿記事を再編集しました。